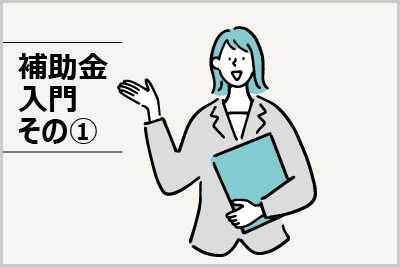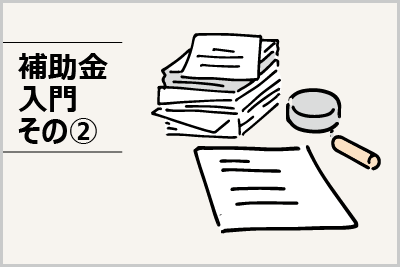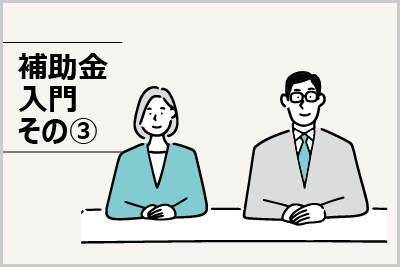2025.09.24
- 製造業
- 事業承継・M&A補助金(旧事業承継・引継ぎ補助金)
支援機関とともに生産性向上に取り組む企業事例(株式会社和田挽物)
地場製造業後継者の「覚悟」と寄り添い支援する伴走支援機関

燕商工会議所 総務課 課長 早川 洋介氏(右)
この記事のポイント
- 先代が経営する会社に入り、現場視点で事業の課題を捉えた後継者
- 覚悟を持って事業を変える後継者と寄り添い支援する経営指導員
- 地域の産業特性を踏まえた支援の仕組みづくり、支援人材育成を行う商工会議所
金属加工が盛んな新潟県の燕三条地域で小型部品の加工を営む株式会社和田挽物は、令和元年に事業承継を行い、現代表の長谷川哲和氏が事業の拡大と変革に挑戦している企業である。当地に立地する燕商工会議所は、変革に挑戦する経営者の構想を理解し、各種の施策を提案しながら、その取り組みを的確に支援し続けている。本記事では、覚悟を持った経営者の挑戦と、経営者を支える支援機関の取り組みを紹介する。
20歳の決意。会社を継ぐ前に見た外の世界

株式会社和田挽物は、先代の和田節夫氏と現代表の父が共同経営者となり、1981年に有限会社和田として創設され、洋食器の持ち手部分の加工事業を開始した。現代表の長谷川哲和氏が当社に入社したのは2001年であり、代表が20歳の時期である。高校を卒業した長谷川氏は、東京に出て働くことを選択し、さまざまな仕事を経験した。
「幼少の頃、父が経営する工場に出入りし、掃除や雑務を手伝った経験があります。いずれは自分もここで働くのだろうなと、うっすら思っていた記憶があります。ただ、学校卒業後にそのまま父が経営する工場に入社することに抵抗を感じ、一度東京に出て働いてみることにしました」
働くうちに、いずれは自分自身が会社を経営する立場になりたいと考えるようになった。
「ゼロから事業を立ち上げていくには、相当な時間とエネルギーを消費する必要があります。自分には、親の会社で働く選択肢もあり、それは自分のキャリアのベースになる可能性があるのではないかと考えました。」
覚悟なき入社時代。現場で見た会社の課題
入社当時は、現場での仕事を覚えることで精一杯であったと長谷川氏は振り返る。職人気質の父が、トップダウンで会社を経営する中、従業員が入社しては退職するという光景を幾度となく目にしてきたという。
「従業員同士の仲は良かった記憶はあるものの、会社に理念やビジョンはありませんでした。今思うと、社長から現場の従業員まで、ただ目の前の仕事を必死にこなしていただけだった気がします。」
せっかく仕事を覚えた従業員が退職していく背景には、従業員本人の側からすると何らかの理由があって「辞める」という行動を起こすわけで、会社の組織風土としての問題があったのではないかと長谷川氏は考えている。
また、現場で働く長谷川氏自身が、目上の従業員と衝突し、結果としてその従業員が退職してしまった出来事も経験している。
「日々、各々が目の前の仕事を一生懸命やっていて、その中でお互いの意見がぶつかってしまう。そして、人が辞めていく。ああ、また辞めてしまったなということを都度感じていました」
当時の自分には、まだ「覚悟」が無かったのだろうと長谷川氏は語る。
理念なき現場から「和のある会社」への転換を目指して
過去の想いを聴く過程で「覚悟」という言葉を複数回使う長谷川氏の真意を聴いてみた。
「何かを成し遂げたい、何かを変えたい、何かを大事にしたいという「本気の想い」が大切だと思っています。「本気の想い」があって何かを言う、行動を起こせば、その言葉を発する人間の覚悟が伴います。逆に、「本気の想い」が伴わない発言や行動では、他人を動かすこともできないし、自分自身の意志も継続できないと考えています。」
2016年に長谷川氏が取締役に就任した当時、会社の方向性について、先代と長谷川氏との間で意見を交わす機会があったという。
「会社の中に“和”を作りたかった。経営の土台となる人の関係性を強くしたいと考えていました」
その「和」を作る手段として、長谷川氏は、従業員同士が交流する懇親会イベントを実施した。
「忘年会は、あえて業務時間中に実施し、飲食にかかる費用も会社負担としました。意図としては、全員参加してほしいということを考えていました。現在でもこの取り組みは続けています」
また、トライ&エラーで新しいことに挑戦して進化をしていくこと、顧客のニーズを理解して顧客に提案しながら自社の事業を変えていくことも重視しているという。
「部品制作を受注して、仕様に沿って生産している事業形態では、新規に生産を打診してくれる顧客のニーズは満たせません。顧客が展開する製品・サービスにあった部品を積極的に提供するため、自社で顧客の要望を取りまとめて、仕様から提案していく必要があります」
その後、段階的に先代から後継者である長谷川氏に会社経営の実務移行が進み、2019年6月、長谷川氏が代表取締役社長に就任した。
会社形態変更と移転に込めた想い。働く未来を描ける企業へ
長谷川氏は代表就任後、有限会社和田の会社形態を株式会社へと変更し、社名も株式会社和田挽物に改めた。
同時に、従業員が当社で働くことで、自分の人生の未来図を描けるような会社にしたいという思いを実現するために、会社の移転を実行した。
新しい取り組みのためにも、機械設備の更新や新規導入が不可欠であったことから、商工会議所に相談しながら、補助金の活用にも挑戦。結果として、補助金を活用した設備の増強を実現した。
当社は、2019年頃からのコロナ禍の影響によって生じたアウトドアブームに乗り、関連製品の加工業務に取り組んだ。しかし、2022年の後半からアウトドアブームが沈静化してきたことを受け、長谷川氏は次の一手として、現在の加工技術よりも精度の高い加工を手掛けることで、これまでは取引を行っていない業界の製造業へのアプローチをしていきたいと考えた。具体的には、半導体製造装置や医療機器の部品に対するニーズがあることを聴いていた長谷川氏は、半導体製造設備に使われる部品の加工受注を目指す方針を打ち出した。半導体製造設備の加工には、これまで以上に精密な加工技術が求められることを踏まえ、3次元測定器機の導入を計画。
2023年5月に公募が開始された「第5回 事業承継・引継ぎ補助金」においては、半導体製造設備部品の加工業務進出の計画を策定し、補助対象経費として三次元測定機の導入にかかる費用を申請し、計画の採択と補助金の交付を受けた。


経営者の構想と伴走支援を実践する商工会議所

「長谷川社長が燕商工会議所の青年部に入会されたのは、今から17年前のことになります。青年部の活動参加を通じ、この地域の他の経営者との接点を築き、商工会議所の役割についても理解を深めていただいた」
と語るのは、当時青年部の事務局を担当していた燕商工会議所 総務課長の早川氏である。
長谷川氏自身も次のように語る。
「商工会議所青年部に参加し、普通の付き合いであれば手の内を明かさないような仕事の内容、例えば、失敗したことから学んだ工程の工夫など、自社だけでは経験できないトライ&エラーの知恵を得ることもできています。補助金の活用についても、同じ経営者同士で情報交換をしています」
燕商工会議所では、長谷川氏の将来の構想を継続的に聴き取り、会社経営の攻めと守りの両面を強化するための対策として、経営力向上計画(※1)や事業継続力強化計画(※2)の策定の取り組みを提案し、支援してきた。
※1 経営力向上計画
経済産業省が認定する計画であり、企業が経営基盤を強化し、持続的な成長を図るための計画である。
※2 事業継続力強化計画
経済産業省が認定する計画であり、企業が災害や緊急事態に対して迅速かつ効果的に対応し、事業を継続できるようにするための計画である。
長谷川氏は次のようにも述べている。
「燕商工会議所の担当者には、特定の補助金の申請のことだけでなく、将来の事業シナリオを話して理解してもらっています。投資に対して補助金を活用する場合でも、当社のシナリオを理解いただいている状態でのアドバイスが得られるため、これまで継続して的確な支援をいただいています」
また燕商工会議所 総務課課長・早川洋介氏も次のように補足する。「補助金申請のための計画書に、展示会に出展して販売促進に取り組むことを記載いただいていますが、今まさに長谷川社長に取り組んでいただいている活動になります。燕商工会議所が出展している全国各地の展示会のみならず、長谷川社長が自ら申し込まれているイベントにも積極的に参加されています」
このように、長谷川氏が自社の構想を商工会議所に継続的に相談し、事業者の構想を踏まえて、商工会議所が事業環境分析から計画策定、販売促進まで広範囲に支援している。また、補助金の計画書に記載している事業計画には、当社の事業展開の進め方が具体的に文書化されており、長谷川氏の活動と商工会議所の継続支援が密接に連携していることがうかがえる。
次なる課題に向けた経営者のチャレンジ

事業承継・引継ぎ補助金の申請時に策定した計画に基づき、半導体製造設備の部品加工、その他の業務受注を獲得するため、長谷川氏は積極的に製品展示会に出展するようになった。
長谷川氏が全国の展示会に出展により、会社を不在にする時間が増えていくことを踏まえ、社内体制の強化に取り組んでいる。
品質管理の強化策として、商工会議所の支援を受けながら燕市ものづくり品質管理制度(TSO)の認証を取得した。
さらに、社員が改善活動に主体的に取り組めるよう社員教育を強化し、品質の国際認証規格であるISOの取得も目指している。人事制度面では、今年度中に経営理念と10年ビジョンを策定し、次年度には経営理念と連動する人事制度の導入にも取り組もうとしている。
長谷川氏は次のように語る。
「社員は、何も働きかけなければ現状からの変化を避ける傾向があると感じています。企業としては、工夫と探求を続けることが、事業を継続していくための必須条件として考えています。設備投資がひと段落した状況にあるので、内部の強化に取り組んでいきます」
これから先、会社を拡大していく構想を持つ長谷川氏は、そのためには会社の土台となる組織や人材を強くすることの重要性を強調する。
「従業員が、自分が勤める会社について誇りを持ち、家族や知人に語れるような状態にしていくべき時期が到来していると感じています」
職員一丸となって地場企業支援を実践する商工会議所
燕商工会議所は、金属加工を行う事業者が集積する管内において、地域密着型の個社支援を徹底する方針を一貫して掲げている。経営指導員には得意とする分野を持ってもらい、会議所内で互いに連携を図りながら、支援の実務経験を積んで成長していくことを推進しているという。
燕商工会議所 事務局長 高野 雅哉氏は次のように語る。
「商工会議所の職員に一番大切だと話しているのは、地場を良くしようという想いを職員一人ひとりが持つことです。商工会議所の活動は、個社支援が基本であり、会議所活動のベースになるものです。経営支援でも、共済でも、手段は異なれど個社の成果に繋がる施策です。個社が良くなることで地場である地域全体も良くなる。この順番を踏まえることが大切です。」
燕商工会議所では、「磨き屋シンジケート」という金属研磨分野の共同受注サイトを運営している。このサイトには11社の事業者が登録されており、各社が提供できる技術分野も登録されている。写真付きのこのサイトを見た海外からの引き合いもあるという。
燕商工会議所 総務課課長・早川洋介氏はこう述べる。
「当会議所が策定する経営発達支援計画(※3)は、事務局長を中心に、現場支援を担当する経営指導員が手分けをして策定しています。経営指導員各々が異なる得意分野を持っており、各分野での施策を計画に盛り込むことを意図しています」
※ 経営発達支援計画
「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」(平成5年法律第51号)に基づき、各商工会や商工会議所が管内の小規模事業者や地域振興のために策定する5年間の事業計画である。
当会議所では、ものづくり産業である燕地区に所在する事業者を積極的に支援するため、設備投資の際に活用できる補助金の申請支援に経営指導員が積極的に応じているという。地域、事業者を深く理解している経営指導員が、経営者の事業構想を丁寧に傾聴しながら支援を行っている。

総務課 課長 早川洋介氏(左)
今回の取材を通じて、ものづくりが盛んな地域で活動する事業者と、それを支える伴走支援を実践する商工会議所が長い年月を通じて強い繋がりを続けていることを確認できた。補助金の適切な活用支援も含め、伴走支援を実践する支援機関の優良事例として、他地域の支援担当者にとっても有益な参考となる内容である。
| 活用した補助金:事業承継・引継ぎ補助金 |
| 年度:2023年(第5回) |
| 枠・型:経営革新枠 |
※本ページに掲載している補助金活用事例は過去の補助制度によるものであり、現在の補助制度とは異なります。
最新の補助要件については、必ず各制度の公式情報をご確認ください。
企業データ
- 企業名
- 株式会社和田挽物
- 設立
- 昭和56年6月
- 従業員数
- 19名
- 代表者
- 長谷川 哲和 氏
- 所在地
- 新潟県燕市吉田法花堂1853-6
支援機関データ
- 支援機関名
- 燕商工会議所
- 所在地
- 新潟県燕市東太田6856